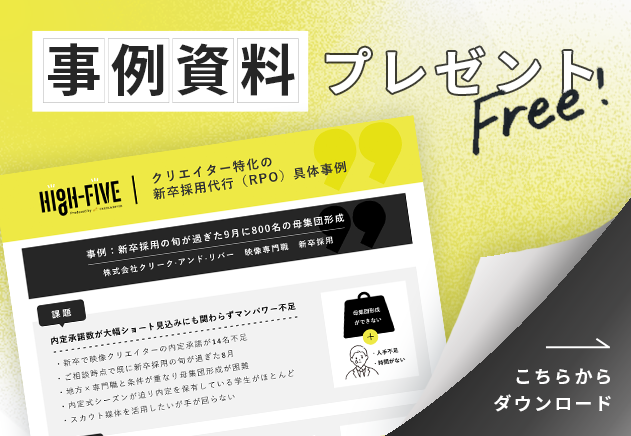公開日:2021/08/17
変更日:2024/08/29
【2024年度】採用手法トレンドとは?手法の変化!採用の見直しが急務!?

2020年春頃から新型コロナウイルスが猛威を振るっており、さまざまな方面に少なからず影響をもたらしています。採用のトレンドもコロナを経て大きく変化していますが、Webでの企業説明会やリモート面接が増加するなど、特にオンライン化が著しく進んでいる状況です。 この記事では、中途採用の観点を踏まえながら、2021年における採用トレンドの紹介をはじめ、自社向けの採用手法を選ぶためのポイントを解説します。
目次
採用手法のトレンドの変化!採用の見直しが急務!?

コロナ発生以降、企業を取り巻く状況は一変しています。人材確保を進めるためには、以下のような現状を把握したうえで、採用の見直しを急がなければなりません。
採用の人手不足で効率化が求められる
コロナによる景気悪化や買い手市場が続いている現状、企業は「採用活動に注力する余裕がない」「人員配置を見直すべき」といった理由から、採用担当を減らそうと動いています。しかし、採用担当が不足すると、担当者一人ひとりの負担が増加するという新たな問題も起こるのです。
この問題を放置すると、担当者の対応ミスや不適切な採用を招いて、採用活動→失敗→再び採用活動……という悪循環に陥ってしまいかねません。
人手不足をどうしても解消できない場合、採用手法の変更・簡素化を図ったり、採用管理システムを導入したりするなど、業務効率を上げる必要があります。採用手法やシステムが変わると、採用担当に求められるスキルも変化するので、それも踏まえて効率化を進めましょう。
コロナの影響で従来の手法が実行しにくい
政府からの外出自粛要請やイベント制限により、2020年から採用に関するオンサイトイベントを開催することが難しくなっています。それにともない、イベントをオンライン化したり、採用手法をオンラインメインに変えたりする企業が増えている状況です。
変化の直後は慣れないこともあってか、企業も求職者も混乱している様子が見受けられましたが、双方ともある程度経験したあとは好印象を感じています。
企業は「イベントの会場費や人件費をカットできる」「採用の間口を広げられる」といったメリットを、求職者は「交通費や宿泊費がかからない」「コロナの感染リスクを下げられる」といったメリットを享受できます。これらを踏まえるとコロナが落ち着いても、オンライン化の流れは定着する可能性が高いでしょう。
候補者へのスピード対応ニーズの高まり
コロナの影響やオンライン化の推進によって、採用市場でのオンライン媒体やツールの活用事例が増えています。これにより各社の採用スピードも上がっているため、対応の遅れが機会損失により一層つながりやすくなったのです。
優秀な人材を逃さないためには、スピーディーに対応できる体制と仕組みを整えたうえで、採用活動に取り組む必要があります。採用手法の流れを把握することはもちろん、自社でしっかり仕組み化することも大切です。
浸透が進む採用・求職活動のオンライン化

企業の採用活動だけではなく、求職者側の活動においてもオンライン化が進んでいます。実際、Webを使ったアプローチが当然のように行なわれているため、企業にとってもはやマスト事項といえるかもしれません。
そこで、採用・求職活動のオンライン化の現況についても解説します。
クラウド型の採用管理システムの活用
スピーディー&スムーズな対応、的確な分析&改善を実現するためには、採用管理システムがとても有効といえます。特にクラウド型のシステムを導入すれば、担当者は勤務場所を問わず作業に取り組めるため、テレワークやリモート面接が推奨されている現状にピッタリです。
採用管理システムの機能や強みはそれぞれ異なるものの、原則として担当者の負担を減らすために作られています。データの蓄積・分析のリアルタイム化や可視化が容易になったり、今まで担当者が行なっていた作業を自動化したりできるため、採用の効率化を図るにあたって必要不可欠です。
なお、導入費用もシステムごとに変動するので、自社のニーズや予算と照らし合わせながら最適なものを選びましょう。
採用プロセス各フェーズのオンライン化
オンラインでの採用活動は以前から行なわれていましたが、コロナをきっかけにその範囲は大きく広がりました。面接や書類選考はもちろん、企業説明会・研修・インターンシップなどもオンラインで実施できるようになっています。
また、採用活動を行なう場合、求職者に連絡する機会も多くなりますが、最近はビジネス用のチャットツールがよく使われています。従来のメールより相互コミュニケーションがとりやすいため、連絡事項をスムーズに伝えたり、求職者の企業理解を促したりすることが可能です。
採用活動のオンライン化は一時的なものではなく、今後も継続して進められる傾向にあるため、未着手なら移行を検討したいところです。
求職者にとってのオンライン採用
オンライン採用のアプローチが増加したことにともない、オンライン化のメリットに気付いた求職者が増えていることも見逃せないポイントです。オンラインで進められる採用プロセスが多いほど、求職者の応募ハードルも下がります。
つまり、遠方・地方からの応募も可能になるため、企業は優れた人材を広範囲から探せるということです。
今後はオンラインで採用活動を済ませられるかどうかも、応募意思を左右する重要なポイントになってくるといえるでしょう。
【2024年】企業が今後取り入れるべき採用トレンド

2021年もコロナ禍は収束する気配が見えないことから、多くの企業において採用手法の見直しや切り替えが行なわれています。傾向的に大勢へのアプローチから個人へのアプローチに移行しているため、それも意識して選定・導入することが大切です。
そこで、2021年5月現在で使われている各手法の概要、メリット・デメリットなどをまとめました。
オンライン採用
その名のとおりWeb上で採用活動を行なう手法です。最近は上記で挙げた部分的な採用プロセスだけにとどまらず、全工程をオンライン化している企業も出てきています。
直接対面する必要がないため、コロナの感染リスクを低減できるのはもちろん、自社から離れた地域の求職者にもアプローチすることが可能です。また、対応がスピーディーに進むので、なかなか時間を作れない転職希望者も応募しやすいでしょう。
ただし、オンライン採用を導入する場合、従来の採用プロセスだと合わないため、採用プロセスの再構築が必要となってきます。
ダイレクトリクルーティング
企業が欲しい人材に直接アプローチをかける手法です。ヘッドハンティングと似ていますが、ダイレクトリクルーティングは外部リソースではなく自社のリソースを用いる点に違いがあります。
自社を知っているかどうかを問わず、優れた人材との接点を作れるため、中途採用で求められる即戦力を確保しやすいことが最大のメリットです。また、企業から積極的に働きかける関係上、採用活動の効果も測りやすいでしょう。
一方、ターゲットを理解したコミュニケーションによる信頼構築が求められるため、担当者に負担がかかりやすいことはデメリットといえます。
ソーシャルリクルーティング
FacebookやTwitterといったSNSを使ってアプローチする手法です。
SNSはコメントやDMによるコミュニケーションがとりやすいので、求職者の特徴や考え方を把握しやすくなっています。また、無料で登録できること、情報の拡散性が高いことも大きなメリットです。これらのメリットを通じて、ダイレクトリクルーティングに持ち込める可能性もあります。
ただし、時代に即したSNS運用スキルが求められるため、担当者がSNSに慣れていないと導入しにくいのがデメリットです。
リファラル採用
自社の社員に優れた人材を紹介してもらう手法です。
採用コストを抑えつつ、マッチ度の高い人材にアプローチしやすいので、効率よく採用活動を進めることができます。社員を通じて入社するため、転職後も馴染んでもらいやすいでしょう。また、採用市場にはいない、潜在的な人材に出会える可能性があることもメリットです。
一方、社内に紹介しやすい雰囲気と仕組みがないと、社員が動きにくいというデメリットもあります。
採用オウンドメディアの運用・運営
自社の魅力が伝わる採用メディアを作って、求職者にアピールする手法です。自社ホームページやブログはもちろん、採用案内動画やWeb説明会・セミナーの録画なども活用します。特に動画は言語化しにくい部分も伝えやすいため、非常に有効なアプローチです。
また、求職者の多くは応募前にWeb上で情報収集を行なっているので、オウンドメディアがあれば採用ブランディングができます。
ブログやオウンドメディアは継続必須ですが、採用とともに人材の定着やエンゲージメント向上にも寄与するため、手間をかける価値はあるでしょう。
自社に合う採用手法を選ぶためのポイント

採用を成功させるためには、現状のトレンドを考慮しつつ、自社の状況に合う手法を取り入れることが大切です。手法選定のポイントもまとめたので、ぜひ参考にしてみてください。
自社の状況と採用活動を明確に把握する
適切な採用手法を選ぶためには、自社の状況および採用活動の内容をきちんと把握したうえで、それを軸に選定・検討を進める必要があります。何の軸もなしに手法を決めてしまうと、導入後に思わぬコストや手間がかかったり、思うような成果を得られなかったりする可能性が高いからです。
どのような人材が欲しいのか、どのポジションで働いてもらうのかといったことを先に細かく洗い出せば、自社が導入すべき手法もイメージしやすくなります。
コストと費用対効果を見る
採用手法を選定・検討する場合、コスト面の考慮も忘れてはいけません。自社が持っている時間・人員・工数などを踏まえつつ、予算に見合った成果が得られるような計画を立てる必要があります。
最近は継続するほど成果が出やすい手法も増えてきているため、その時・その回だけではなく、中長期的な観点から判断することが大切です。優れた人材を採用できたとしても、コストに対する費用対効果が低い手法なら継続すべきではありません。
手法によってコストも費用対効果も大きく変動するので、無理なく運用・継続できるかどうかを念頭に置きながら、自社にとっての最適解を見つけましょう。
なお、高度な採用スキルや専門性が求められる層をターゲットにする場合、上記の手法より人材紹介やエグゼクティブサーチのサービスを使ったほうが、総合的なコストを抑えられる可能性があります。必要に応じて、こちらの手法も検討しましょう。
採用スキルが確保できるか
採用に関わる担当者が流動的だったり、最近のトレンドに沿った担当者がいなかったりするという理由で、採用スキルに不安を感じている企業は少なくありません。
採用活動に役立つシステムやサービスがあるとはいえ、それを使うのは人間です。自社向けの手法を導入しても、担当者の採用スキルが不足していると、計画が途中で滞ったり、求職者とのミスマッチを引き起こしたりする可能性があります。
このような問題を避けたいなら、外注してでも採用スキルを確保すべきです。特に近年はRPOサービス(採用代行サービス)が注目を集めており、実際に活用している企業も増えてきています。それなりの外注コストはかかりますが、費用対効果に優れているうえ、採用トレンドをいち早くキャッチアップできるため、検討する価値は高いでしょう。
あるいは導入する手法に合わせて、新たに担当者を採用するのも一考です。ただし、外注のように合わなかったら解約ということはできないため、リスクは大きいといえます。
単体より複数の組み合わせを考えてみる
採用手法はたくさんありますが、単体ではなく複数を組み合わせて使うこともできます。同時並行しすぎて手が回らなくなるのは問題ですが、オンラインの手法なら連携しやすいため、効率化につながる可能性も高いでしょう。
例えば、ソーシャルリクルーティングと採用メディアを組み合わせれば、SNSの拡散力を活かして自社コンテンツを広めるといったことが可能です。
まとめ
2020年から続いているコロナの影響もあって、採用手法のトレンドは「オンライン化」が進んでいます。インターネットやスマートフォンがますます発展しているデジタルの時代、さらにスピーディーな対応が求められる可能性もあるので、今までの手法を続けていると、応募自体が来なくなるかもしれません。
自社が欲する人材と出会うためには、時代の流れや自社のニーズに即した手法を取り入れたうえで、求職者にアプローチすることが大切です。コロナが落ち着いてからも、オンラインでの採用活動は定着すると考えられるので、もしオンライン化が進んでいなければ、この機会に検討することをおすすめします。
どの採用手法を選定すべきか決められなかったり、運用するにあたって問題を抱えていたりする場合、コンサルタントへの相談も検討してみましょう。
特にクリエイターやIT・Web系の人材を求めている企業様ですと、当社が運営する『HIGH-FIVE[HR]採用戦略・採用代行(RPO)サービス』にてご相談することができます。以下のようなサービスを提供しています。
・採用戦略立案・人材要件定義(採用活動全体の設計)
・採用マーケティング(会社の魅力を伝える)
・採用ブランディング(入社意向を高めさせるための企業ブランディング)
・採用プロモーション(母集団形成するためのプロモーション)
・選考見極め、惹きつけなど。
採用戦略立案から施策実行までを一気通貫で行なうことで、企業様の目的に合わせたに最適な採用方法を実現します。これまでのノウハウや充実したバックアップ体制を駆使し、採用に悩む企業様の問題解決をサポートします。
ぜひ、クリエイター・IT人材の採用でお困りの人事担当者様は、『HIGH-FIVE[HR]採用戦略・採用代行(RPO)サービス』にご相談ください。

この記事を書いた人
大学を卒業後、関西の広告代理店へ入社し、営業として求人媒体の広告販売や雑誌メディアの広告販売、SPツールの企画、提案、制作進行管理を4年ほど経験。クライアントは地元関西の企業や飲食店、美容室などがメインでほぼ新規での営業を経験。その後、クリーク・アンド・リバー社へ転職し、13年...
![HIGH-FIVE[HR]](https://hr.high-five.careers/wp-content/themes/creek_original/images/hr_new/hr_logo.png)